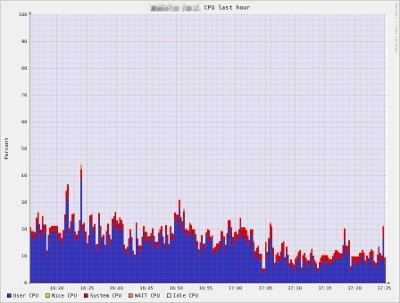古くからのHP Proliantユーザーにはアタリマエのことかもしれないが、新参者のProliantユーザーにはよくわかんないことが割とある。例えば、SmartArrayカードで組んだRAID Arrayの監視だ。
RAIDの管理コマンドを使えば、RAIDの設定などが割と簡単にできることはわかったけれども、どうも監視についてはどうもピンと来ていないたぶん、ドキュメントは存在している感じだが、まとまった形でドキュメントが用意されていないような気がするのが原因ではないか(*1)。どうやら、IMAなるものをインストールすれば、ハードウェアの監視を一括で引き受けてくれるっぽい。で、何か起こったら、rootへのメールと、/var/log/messageへの書き込みを行なってくれるらしい実際にメッセージを書きだすのはIMAの構成モジュールのASRらしいが(*2)。
ただ、なんとなくここまで大掛かりに監視したくないような気もする。監視用のエージェントがメモリとかCPUとか食わないだろうかといった心配もあるし、単にRAIDがコケてないことを確認したい場合の選択肢がないか、と探してみたら、SourceForgeにccissドライバと共に公開されている「cciss_vol_status」ってアプリケーションを使って、RAID Arrayのステータスを取得して、そのメッセージをどうにかすれば監視ができそうだ。
例えば、「cciss_vol_status」を実行しつつ、メッセージを取得して、取得した結果がおかしなことになっていたらアラートを上げるみたいなシェルスクリプトをcronで定期実行するのもありかなぁという気もする。
で、試しに「cciss_vol_status」をビルドして実行してみようとしたら、「/dev/cciss/c*d0」なんてデバイスが存在しないのだった(汗)Scientific Linux6を使っている関係で、ccissドライバではなく、hpsaドライバが使われているせいだろうけれど。。。で、ドキュメントを読んでみたら、hpsaドライバを使っている場合は、scsi genericデバイスが割当てられるらしく、「cciss_vol_status /dev/sg0」とかやると、RAID Arrayのステータスが返ってきた。ま、あとはシェルスクリプトを書くだけ、と。
*1:たぶん、ドキュメントは存在している感じだが、まとまった形でドキュメントが用意されていないような気がするのが原因ではないか、と
*2:実際にメッセージを書きだすのはIMAの構成モジュールのASRらしいが