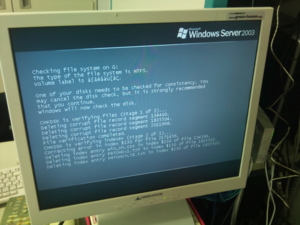さて、DNSサーバをどうしたもんだか、ぼんやりと考えている。Webでサービスを提供するための前提条件みたいなものだから、非常に重要…ではあるけれど、冗長構成が前提なDNSサーバーがどうにかなって困ると言うことはあまりないせいか、その重要性が理解されづらい。
また、DNSサーバに求められる要件も特段ややこしいことはなく、普通に落ちない鯖であればokで下手なハイエンドマシンなんかもったいない…そんな感じがDNSの存在を埋没させてる気がする。
要するに、いちいちサーバを用意したりするような手間はかけたくないが、ちゃんと動いてて欲しいのがDNSサーバーと言うことになる。
そう考えてみると、極めて簡素にDNSだけ預かりますってサービスに預けてしまうのが手っ取り早いが、フツーのレンタルサーバサービスではDNSだけってサービスは意外と提供されていない。そこで、クラウドである。
AmazonのAWSで提供されている「Route53」っていう名前のDNSサービスが、まさにそのサービスだった。しかも、しばらく前まではAPIしか提供されていなかったのだが、改めてWebの画面が提供されたことで簡単にゾーンファイルを編集できるようになった。
しかも、「Route53」は、世界各地のAWSの拠点において、anycastで提供されているわけだら、ネットワーク的な遅延なども少ないし、冗長性も確保されているだろう。しかも、1ドメインが$0.5くらいで提供されているというのがまた魅力的だ。いくつかのドメインを持っているとしても、「Route53」と単純に価格比較したら、わざわざDNSサーバを購入する妥当性は生まれてこないだろう、という気がする